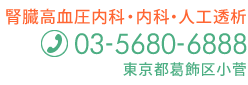2023年5月8日から、感染状況やワクチンの普及、経済活動などの観点から、新型コロナウイルスは5類感染症に分類されることになりました。
しかし、慢性腎不全の患者様、特に透析治療においては感染および増悪のリスクが高まることが懸念されます。
そのため、ご来院時および送迎車内でのマスク着用、入室時の手指アルコール消毒、体温測定を引き続きお願いいたします。また、ご自宅で発熱などの症状がある場合は、必ずご来院前のお電話をお願いいたします。感染検査や来院時間の変更、感染防御シェルター利用などの対策をご案内いたします。
皆様のご理解とご協力をいただけますよう、お願い申し上げます。
患者様とスタッフの安全を第一に考え、感染拡大の予防に最善の努力を払ってまいります。
2026.1.1
新しい年を迎え、患者の皆さま、ご家族の皆さまにご挨拶申し上げます。
透析治療は、特別な出来事ではなく、日々の生活を支えるために欠かせない医療です。
一年を通じて、決まった時間に通院し、治療を続けてこられたことは、決して簡単なことではなく、皆さまのご努力に心から感謝しています。
年のはじめは寒さが厳しく、体調を崩しやすい時期でもあります。
冬場は血圧の変動や感染症、食事量の変化などが、透析治療に影響することもあります。
「いつもと少し違う」「何となく調子が悪い」と感じることがあれば、どんな小さなことでも構いませんので、遠慮なくスタッフにお声かけください。
日々の小さな変化を大切にしながら、安定した治療につなげていきたいと考えています。
本年も、医師・看護師・臨床工学技士をはじめ、スタッフ一同、変わらず丁寧な診療を心がけ、患者の皆さまの日常を支えてまいります。
2025.08.18
今年の夏は全国的に非常に暑く、気温が40度を超える日もありました。
汗をかくことが増えていますが、汗に含まれる「塩分」についてご存じでしょうか?
実は、汗1リットルあたり約3~4gの塩分が失われると言われています。 CKD(慢性腎臓病)の方にとっては、特に気をつけていただきたいポイントです。
1日の塩分摂取量の目安は6g程度ですが、発汗量に応じて見直すことも必要です。 運動量によって差はありますが、運動中は1時間で1~3リットルの汗をかくこともあり、その分だけ塩分も失われます。
また、服用している薬の中には、以下のような作用を持つものがあります。
①塩分の排泄を促す薬
②塩分の吸収を抑える薬
③水分を体内に保持し、塩分濃度を下げやすくする薬
CKDの方には、①のような薬が処方されていることが多く、これは高血圧の治療に有効な一方で、発汗による塩分喪失と重なるとリスクが高まります。特に、減塩食を徹底している方が大量の汗をかき、このような薬が効いていると、血中のナトリウム濃度が過度に低下し、大変具合が悪くなることがあります。
■CKD患者さんへのお願い
CKDの患者さんが、大量に汗をかくような運動や生活をされる場合は、十分な注意が必要です。また、高齢の方では体内の調整機能が落ちているため、自覚がないまま脱水や低ナトリウム状態に陥ることがあります。
「暑く感じないから」といって、室温が30度を超えるような環境で過ごすのは避けてください。
引き続き、体調管理に十分ご注意のうえ、残暑を健やかにお過ごしください。
2024.10.29
成人のおよそ5人に1人が慢性腎臓病(CKD)と診断される時代になりました。特に、尿に蛋白が出ている場合は注意が必要です。慢性腎臓病とは、3か月以上続く蛋白尿または腎機能低下です。
■蛋白尿または腎機能低下が続くとどうなる?
尿に蛋白が出続けると、腎臓の機能が次第に低下していくことが考えられます。腎機能が持続的に低下すると、腎不全に至り、命に関わるため、透析などの代替療法が必要になることもあります。
■早期発見のために健診を
腎臓病の早期発見には、検尿を含む定期的な健康診断が非常に重要です。健診により、腎臓病の初期段階や腎機能の軽度の障害を見つけることができ、進行を防ぐ対策を講じることが可能です。
病院に通院中の場合でも、尿や腎機能を定期的に診てもらっていない場合は健診が必要です。
■健康診断で蛋白尿が出ている、または、腎機能に異常があったら?
健康診断で尿に蛋白が出ている、または腎機能に※印がついていた場合は、放置せずに専門の腎臓内科を受診することが非常に重要です。腎臓内科では、腎臓に問題があるか、その原因を詳しく調べ、早期に治療方針を決定することで、腎機能の悪化を防ぐことができます。
専門医による適切な診断と治療が、腎臓の健康を守り、さらなる進行を防ぐための鍵となります。少しでも気になることがあれば、早めに腎臓内科外来での受診をおすすめします。